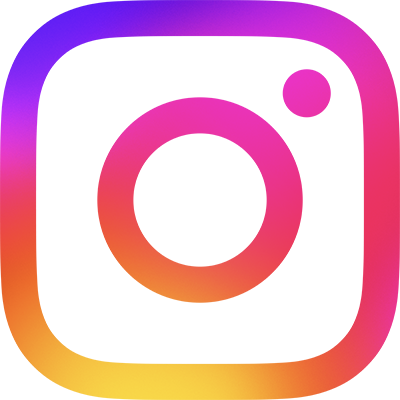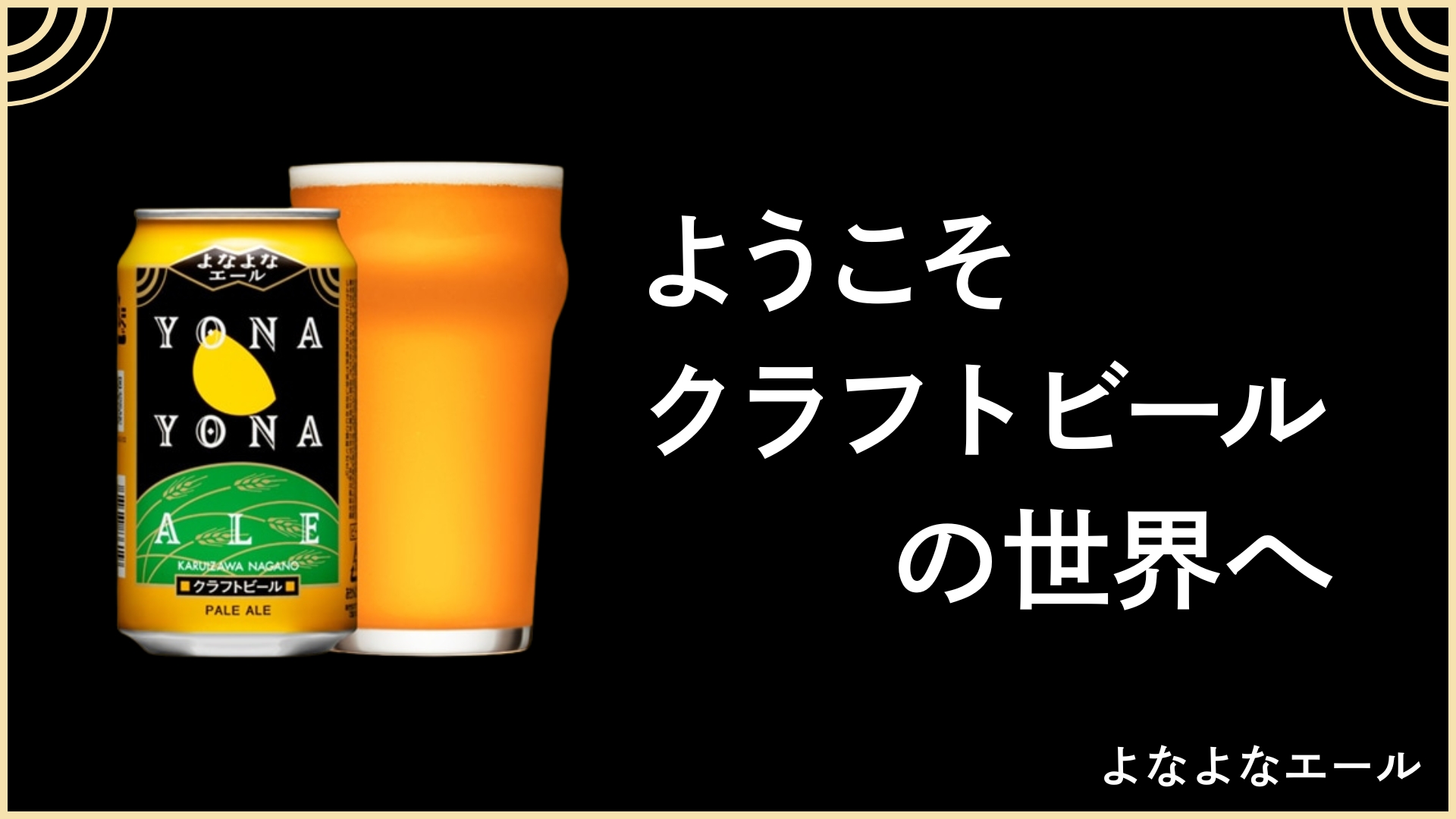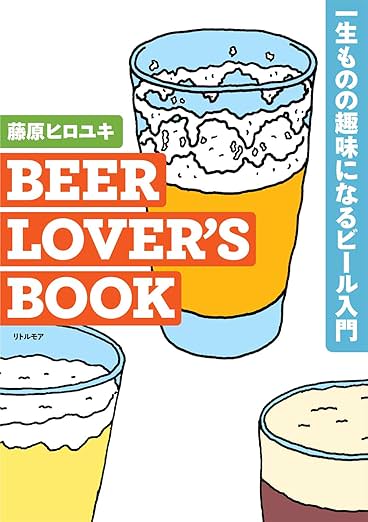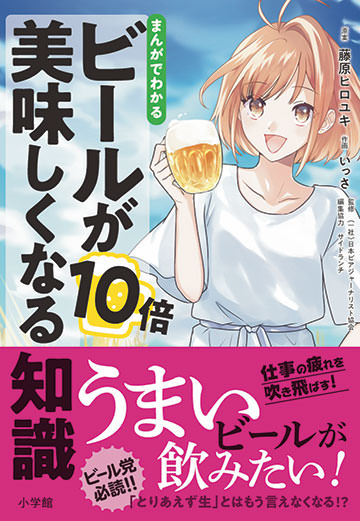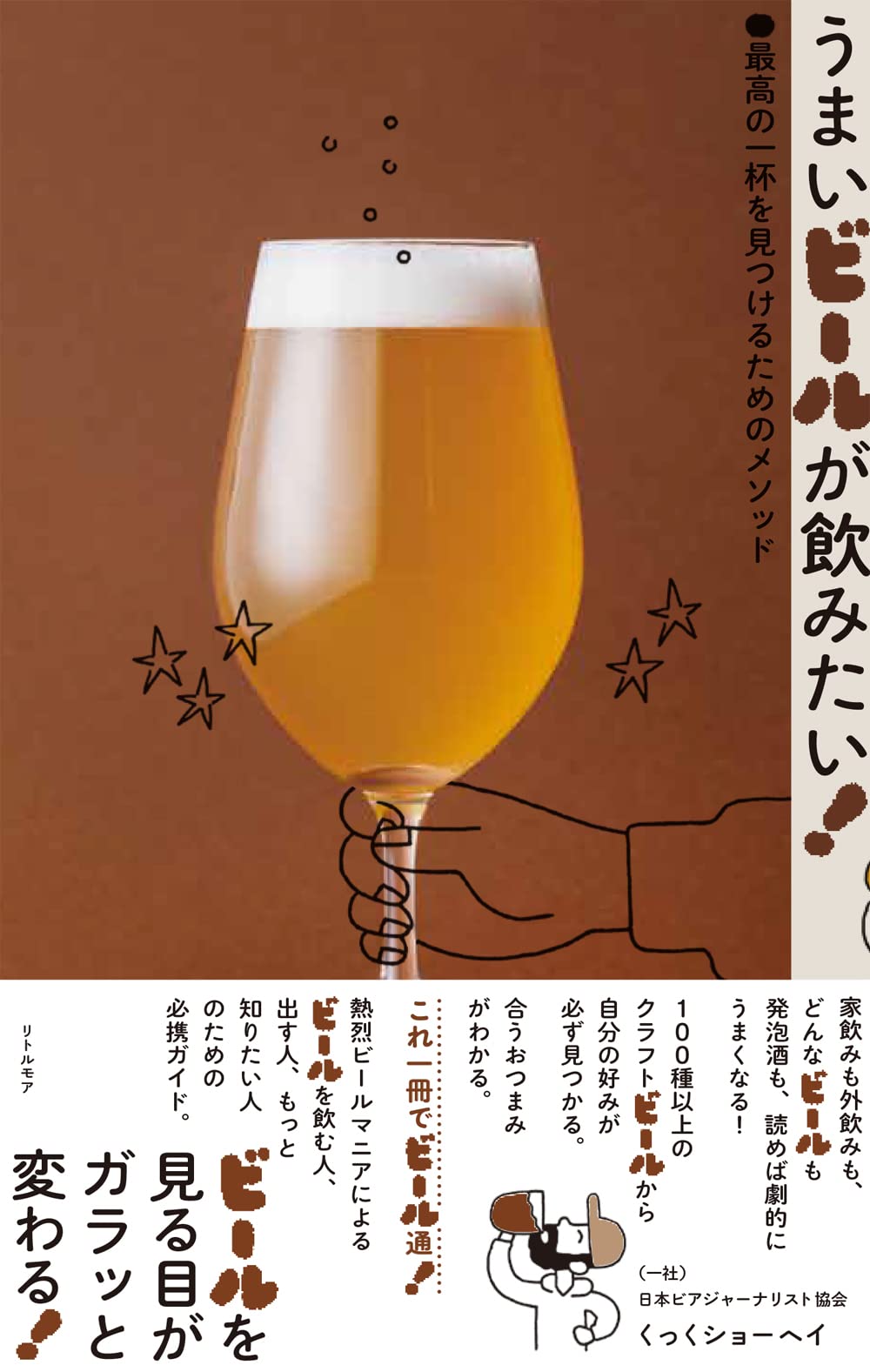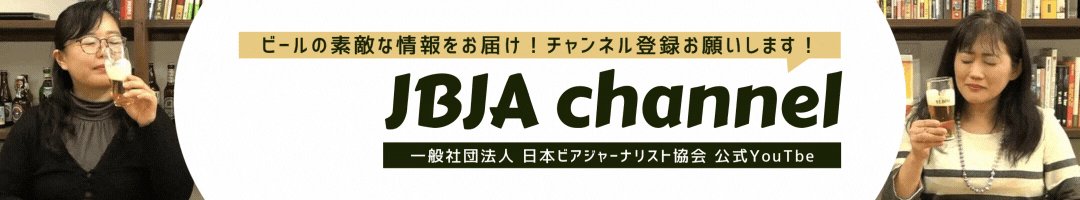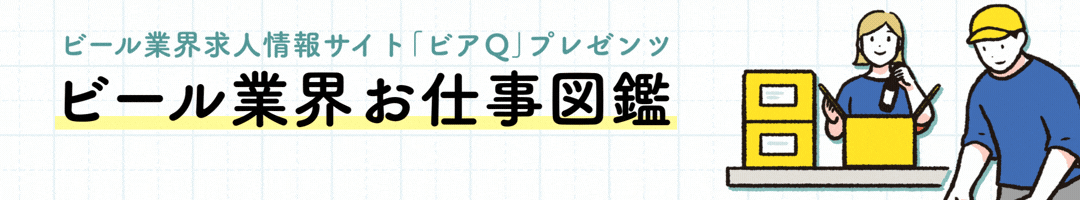ビールを運んだ路面電車、その廃線跡をたどる
日本のビールの歴史をひもとくと、1870年にウィリアム・コープランドが、横浜居留地(現在の山手町付近)で「スプリングバレー・ブルワリー」を創業したとある。1885年には「ジャパン・ブルワリー・カンパニー」に引き継がれ、1888年に商品名「キリンビール」を発売。そして1907年には「麒麟麦酒株式会社」が設立され、横浜山手工場として事業を継承し、現在につながる。
一方、横浜の街の発展に伴い、路面電車が運行を開始したのは1904年。路線を徐々に拡大してゆき、元町地区から本牧方面への「本牧線」が開通したのが1911年のこと。その2年後の1913年より、この本牧線が、ビールの輸送に使われ始めたのである。

青線で示したのが路面電車の本牧線で、赤線がビール輸送のために敷かれた路線。工場から本牧線までと、本牧線から船着場までの2か所。トラックも普及しておらず道路事情も悪かった当時は、大八車で原料の麦やホップを工場まで運び、製品となったビールを運び出していたとのこと。路面電車での運搬が始まったことで、その苦労は大きく緩和されたことだろう。
しかし1923年の関東大震災で、横浜山手工場が倒壊。現在のキリンビール横浜工場(鶴見区生麦)の地へと移転するのである。ビール輸送に路面電車が活躍したのは、わずか10年余りであった。当時に想いを馳せながら、その跡をたどってみた。
横浜市電保存館

最初に向かったのは「横浜市電保存館」。7両の車両が保存されており、また、横浜の交通網と街の発展に関する展示も充実しており、楽しみながら横浜の路面電車の歴史を学ぶことができる施設だ。

保存車両のうちのひとつが、この「無蓋貨車」。まるで軽トラのお尻をつなぎあわせたような、ユーモラスな姿の車両は、貨物専用の車両である。展示してあるこの車両は昭和23年に製造されたもので、戦後の復興に活躍した車両とのこと。実際に明治から大正時代にかけてビールを運んだ車両は、さすがに残っていない。しかし、このような形の車両がビールを載せて走っていたのだと思い、しばしノスタルジーに浸る。
船着場跡地

さて、いよいよ廃線跡を歩いてみる。最初に向かったのは、ビールを出荷するために船に積んだとされる船着場のあたりである。JR根岸線の石川町駅に程近い、中村川の河岸に貨物駅があったとのことだ。奥に見える「西の橋」は路面電車も走った幹線道路で、その付近から貨物駅へと線路が通じていたらしい。

現在は遊歩道が整備されており、当時の面影は全く残っていない。100年以上も前に、この場所で「キリンビール」が貨車から船へと積み卸しされていたのである。ビールに限らず、物資の運搬にかかる労力は、トラックが物流の主役となっている現在からすると、想像し難いほど大変なものだっただろう。
元町付近

路面電車は元町付近から本牧方面へ向かっていた。現在はショッピングストリートへ向かう人たちが行き交う繁華街である。居留地に近いこの辺りは、昔は外国人と日本人が入り混じって歩いていたのだろうか。
山手隧道

路面電車を本牧方面へと建設する際に、山手地区の丘を抜けるための電車専用のトンネルが掘られた。写真の、現在の「第二山手隧道」である。ちなみに「第一山手隧道」は、関東大震災後に道路専用トンネルとして、電車のトンネルに並行して作られた。路面電車が廃止された後は、2つのトンネルが道路の上下線としてそれぞれ一方通行になっている。新しいほうのトンネルが「第一」を名乗っているのは、道路トンネルとして使われ始めた順序である。
本牧通り

トンネルを抜けると、道路の名前は「本牧通り」となる。現在は片側2車線の幹線道路で、市営バスが頻繁に行き交っている。ちなみに、この付近の地名は「麦田町」、ビールに縁を感じるではないか。

ところで、東京の人ならば青い帯の電車の「京浜東北線」はおなじみだろう。しかしそれは系統の通称であり、走る線路の正式名称は別だ。北側から、大宮駅から東京駅までは東北本線、東京駅から横浜駅までは東海道本線。そして横浜駅から先、大船駅までは根岸線である。この付近に根岸線が開通したのは1964年。それまでは路面電車が主要な交通機関だったのだ。
引き込み線跡

ここは「北方小学校入口」交差点。路面電車の本牧線から、横浜山手工場への引き込み線が分かれていた場所だと思われる。

本牧通りから横浜山手工場へと向かう道は、最初は平坦だが途中から上り坂となる。実は、路面電車の本牧線から工場までの引き込み線が、どの程度の距離だったか定かではない。いくつかの資料を見ても、その数字はバラバラである。この坂を見ると、路面電車の勾配としては非常に急である。原料やビールを積んだ当時の電車が、この坂を上り下りできたのかは疑わしい。線路の終点はどこだったのか、工場の敷地がどこまで広がっていたか。謎に包まれている。
キリン園公園

坂を登り切った辺りに、小さな公園がある。その名も「キリン園公園」。道を挟んだ隣は小学校で、そことあわせて広い工場の敷地が広がっていたとのことだ。

園内には大きな石碑があり、「麒麟麦酒開源記念碑」とある。明治時代にキリンビールの歴史が始まった場所では、令和の子供たちが元気よくサッカーで遊んでいた。現在のキリングループはサッカー日本代表のスポンサーである。サッカーに夢中の子供たちは、ここがキリンの歴史が始まった場所であることを知っているのだろうか。

取材を終えて、久しぶりにこのビールが飲みたくなった。「キリンクラシックラガー」である。レトロなデザインの缶を愛でつつ、クリアな苦みがしみじみと美味いこのビールを味わいながら、ビールを運んだ路面電車に想いを馳せる。いくらビールを造っても、運ぶ手段が無ければ、飲み手に届くことはない。運搬に関わる先人たちの知恵と苦労があったからこそ、現在の我が国のビール文化はある。
参考資料
横浜市電保存館
https://www.shiden.yokohama/
キリン歴史ミュージアム
https://museum.kirinholdings.com/
かつての横浜市民の足「市電」にまつわる6つの謎
https://toyokeizai.net/articles/-/784032
【写真は全て筆者撮影】
※記事に掲載されている内容は取材当時の最新情報です。情報は取材先の都合で、予告なしに変更される場合がありますのでくれぐれも最新情報をご確認いただきますようお願い申し上げます。