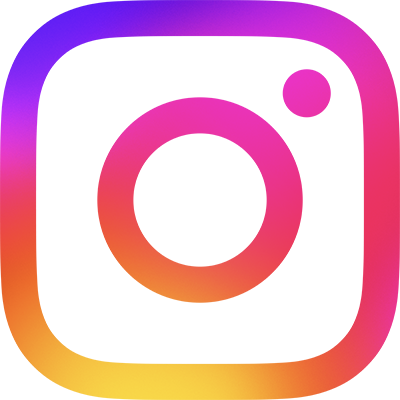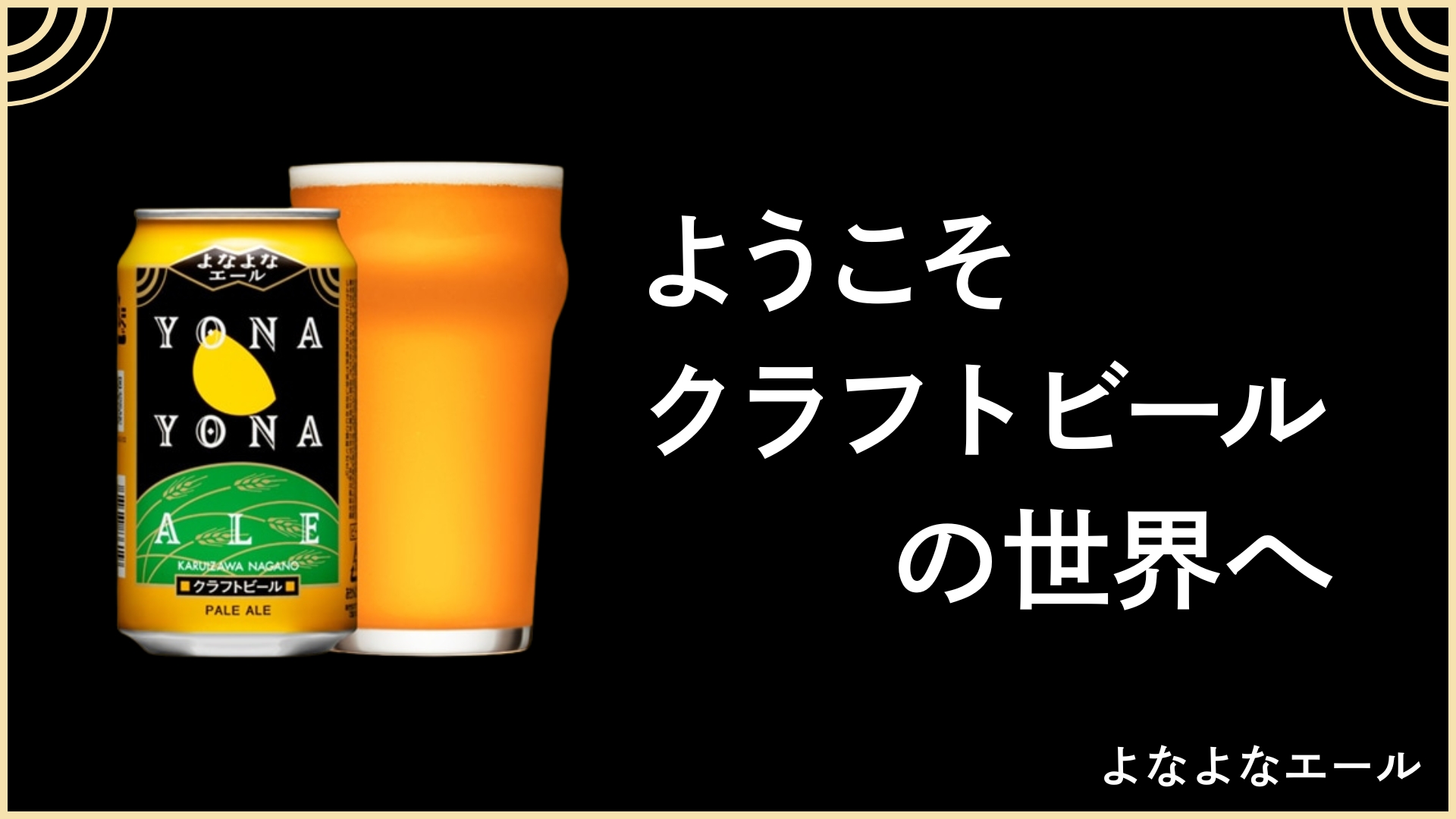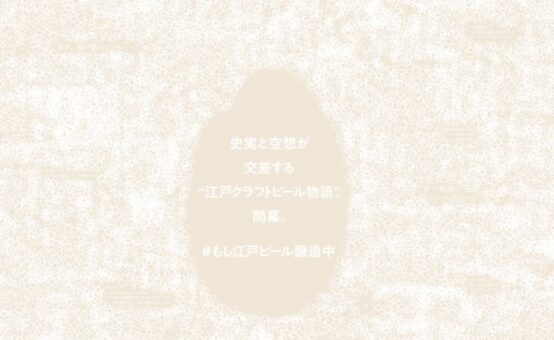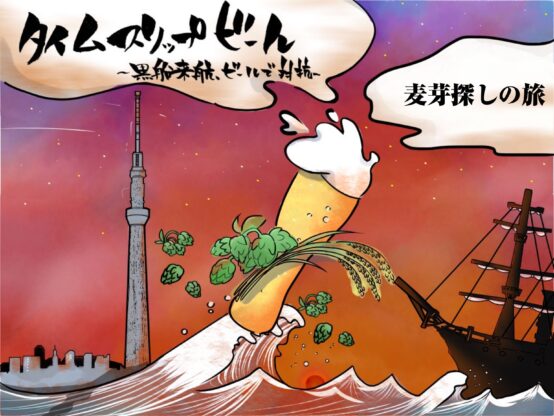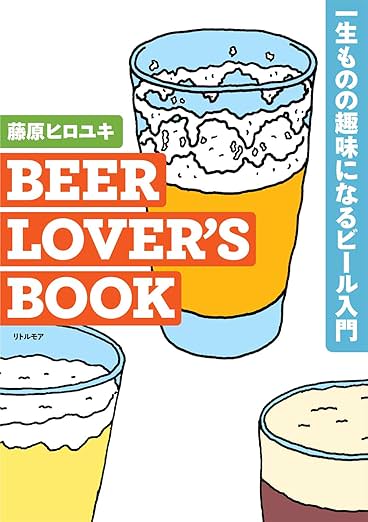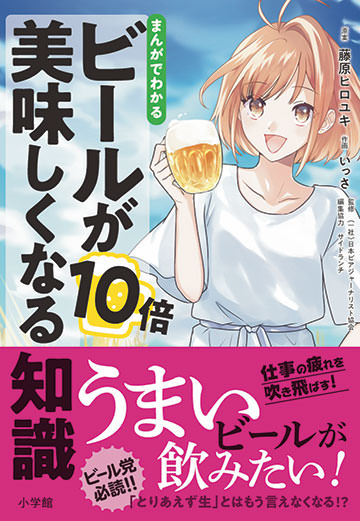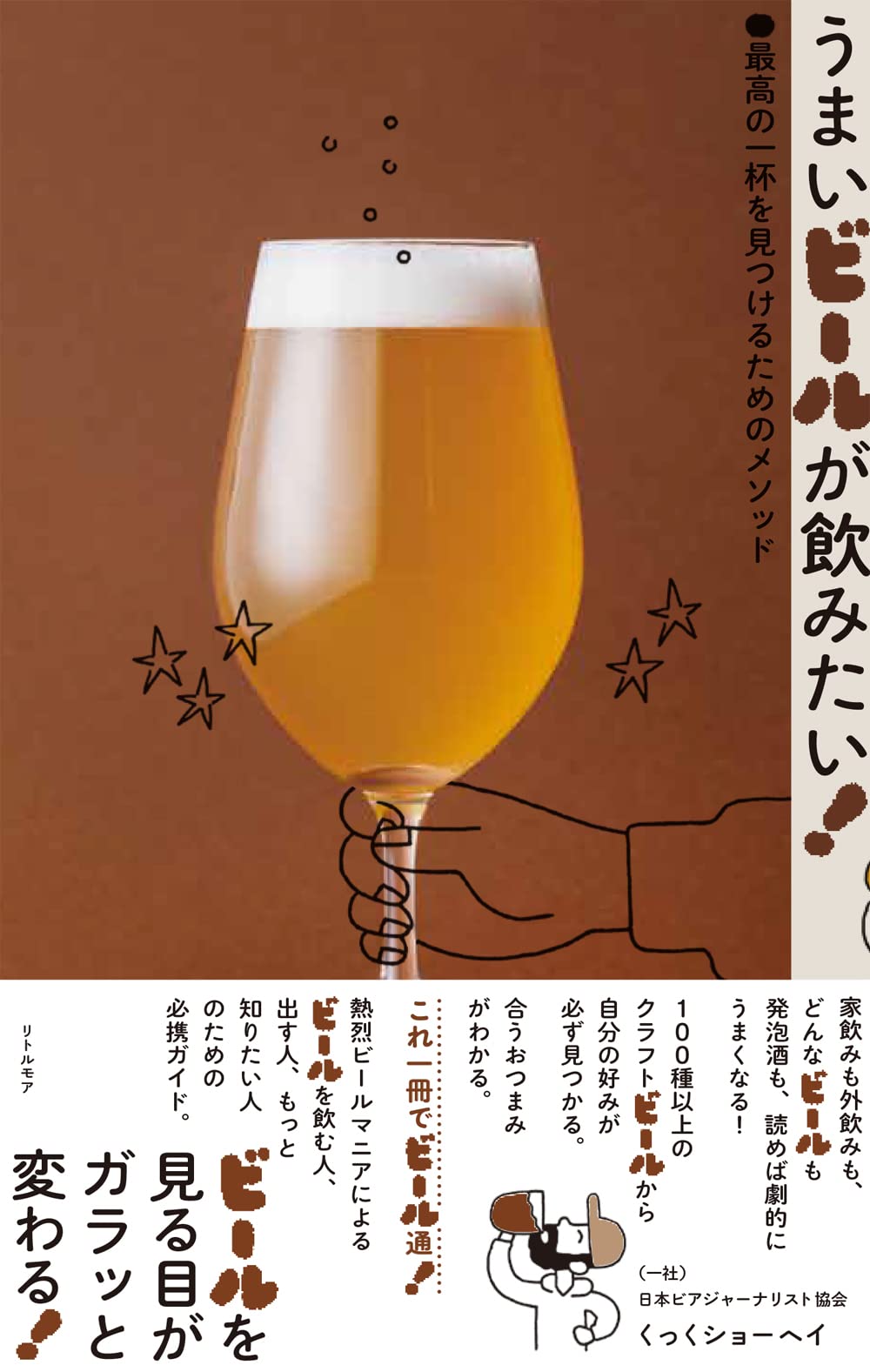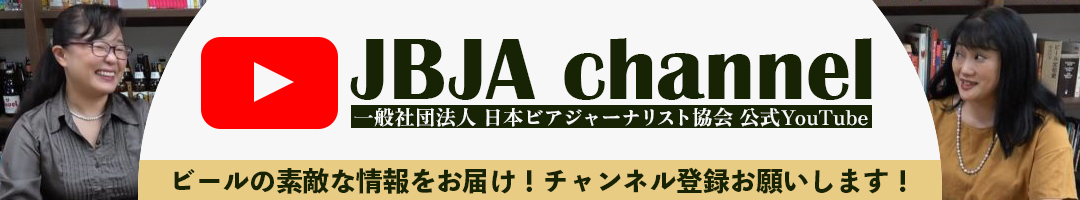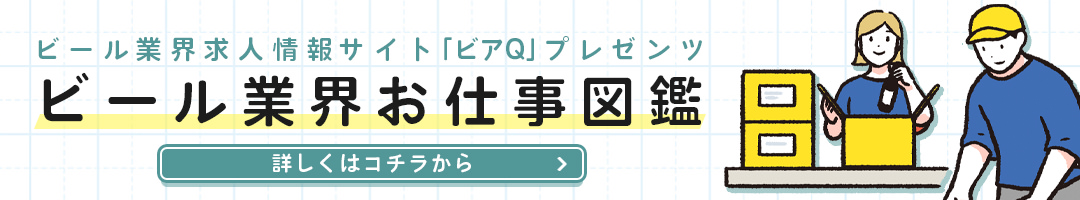さくらんぼ生産者としてビール作りに係わった感想
私はさくらんぼ生産者です。
さくらんぼについて
さくらんぼには多様な品種があります。高価な品種として「南陽」や「佐藤錦」は広く知られていると思います。さくらんぼは、例えば南陽の木だけがあっても実は成りません。他の違うさくらんぼの花粉を付けなければ、実は成りません。そのため、南陽の木に別な種類のナポレオン等を接ぎ木するか、そばにそれらの木を植えて花粉付けをする必要があります。佐藤錦も同様です。私達のサクランボは全て接ぎ木で行っています。

赤い印がナポレオン佐藤錦に接ぎ木
そのため、ナポレオンは花粉付けが終わり実が成ると実を落とす作業をしなければなりません。ナポレオンは甘みと酸味のバランスは良いのですが製品としては南陽の2割程度の値段しかなりません。加工用のジュースやジャムとして使用される程度です。
私は、ベルギービールを飲むようになって、さくらんぼビールが沢山ある事を知りました。
南陽も佐藤錦も甘みが強く酸味が少ない事、製品にしてもハネ(傷や形の悪いあるいは色薄)品でも高く売れるため使用できません。そのため、ビール使用はナポレオンにしました。
ナポレオンを使い一昨年と昨年ビールがそれぞれ完成しました。

一昨年のサクランボビール
さくらんぼビールについて
一昨年と昨年のビールを飲んで感じたのは同じさくらんぼの種類と同じ基礎ベースのビールを使っても味が全く異なりました。でも、ビールは美味しいと思いました。味の違いはベルギービールのランビックの様にビンテージをつける必要があると思うほどです。さくらんぼの出来がビールに出てくると感じました。
一昨年は平年並みの収穫でした。佐藤錦がが終了し南陽が終了し最後にナポレオンの収穫。
昨年は雪解けが早く、枝切りが十分でなかったため、実の成りすぎと葉による日光遮断があり、全体的に小さめで色薄でした。

枝切りと花粉付け
しかも、雨不足のため(さくらんぼ農家には良い)路地ものの収穫が長引き、さくらんぼシーズンが終わっても佐藤錦や南陽が残っている状態のため、さくらんぼの一部が腐って収穫が少ない状況でした。

左昨年右一昨年
農家としては、毎年、農作物同じように育てるのは難しいと感じました。しかし、その農作物を使い美味しいビールににしていくための醸造家の経験と勘は素晴らしの一言だと思います。
今年は昨年の末からの大雪のためハウスの半分が倒壊してしまい、さくらんぼの枝もかなり折れてしまいました。現在のところ、今年はナポレオンを使ったビールは、高級さくらんぼのために花粉付け専用にする予定です。現在、路地のさくらんぼが半数です。成熟して雨に当ると割れてしまいハネ品(ハネの中でも路地のハネはハウスのナポレオンのハネより安い)になってしまい、その製品は長く保存が効きません。路地の製品もハウスの製品が市場に出てきたら、格安になります。そのため、路地のハネ品を使ってビールを造る方向で考えています。来年度にはまたハウスを建て再度ポレオンを使ったビールを造って行きたいと思います。

倒壊したハウス
最後に
農作物(麦やホップやその他の副原料)は、毎年天候によって収穫物の出荷量や味や色が全て変わります。毎年一定にするには生産者の勘や知識が必要となってきます。農作物を一定にしようと努力します。それでも、天気には勝てません。ビール造りをする人は、美味しいビールを造っています。それでも、農作物の出来によって味は変わってしまいます。また、ビールは長期保存が出来ないものもあります。もし、保存ができるのなら飲み比べも良いと思いますが、毎年味が変わるのを感じて頂くのも良いかと思います。
※記事に掲載されている内容は取材当時の最新情報です。情報は取材先の都合で、予告なしに変更される場合がありますのでくれぐれも最新情報をご確認いただきますようお願い申し上げます。