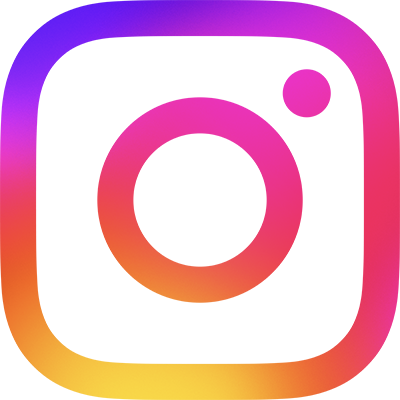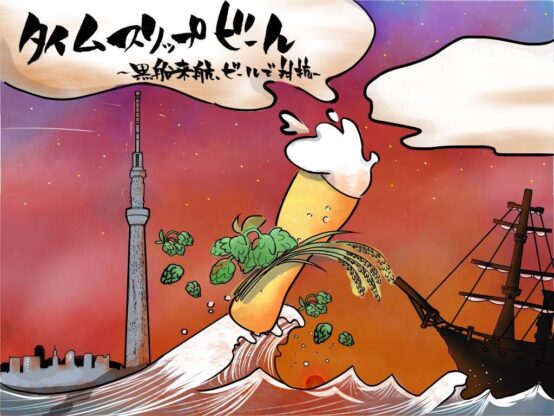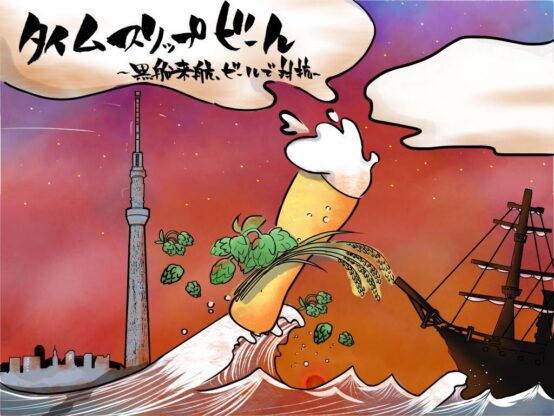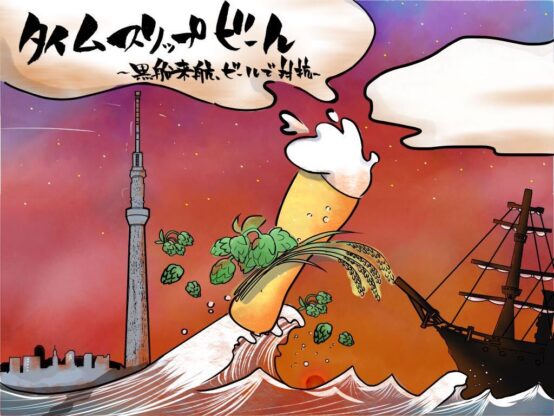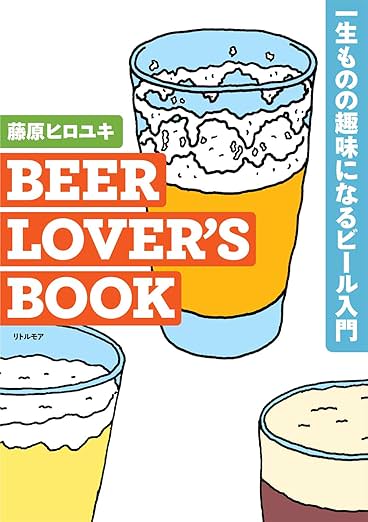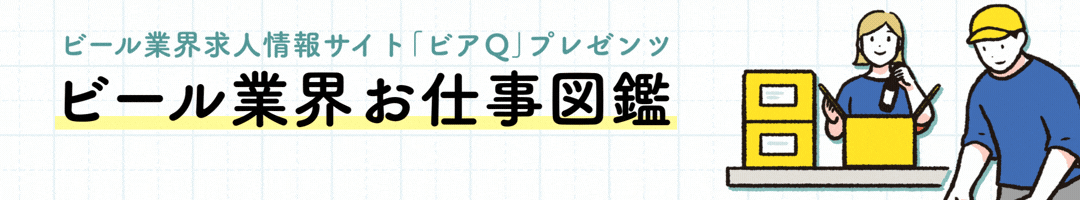【連載ビール小説】タイムスリップビール~黒船来航、ビールで対抗 95~老舗酒蔵の次男、麹で覚醒する 其ノ拾肆
ビールという飲み物を通じ、歴史が、そして人の心が動く。これはお酒に魅せられ、お酒の力を信じた人たちのお話。
※作中で出来上がるビールは、現在醸造中!物語完結時に販売する予定です

前回のお話はこちら
第一話はこちら
まずは試験的に、小さな鍋で麦汁づくりを開始する。湯気のあがる鍋を見ながら、直は首を捻った。糖化で重要なのは温度管理だ。お湯の温度は酵素が働きやすい65℃程度にキープしておきたいのだが、温度計がなければいまの温度がさっぱりわからない。
「なあ喜兵寿、温度は手で測るっていってただろ?あれ、もう一回教えてくれ」
喜兵寿は頷くと、おもむろに鍋の中に手を入れる。そしてそのままゆっくり3度かき回した。
「……これは薄火だな」
「薄火かあ。でもその薄火がなんだかわかんねえんだよな!他にはどんなものがあるんだ?」
「他には『手抜き』とか、『手引爛』とかいろいろあるな。わかりやすいところで言えば、湯がぼこぼこと泡立つ直前は『熱火』だ」
「沸騰直前はわかりやすい!でも65℃、これめっちゃ中途半端だから!」
頭を抱える直を見ながら、喜兵寿は火吹竹で竈の炎を強くしていく。
「お前たちが何を使っているのか知らないが、普段から物に頼るからこうなるんだろ。酒を造るものたるや、自身の感覚を何より大切にするべきだ。湯がどのくらいの熱さかなど、目で、肌でわかるだろう?」
「うっさいなあ!今はそういう話をしてんじゃないんですう!」
直はべえっと舌を出すと、鍋に指を差し入れた。普段入る風呂よりも少し熱いくらいだろうか?だとしたら今は43℃程度で、でも手を入れ続けたとて65℃などわかる気がしない。
温度が低すぎても高すぎても、酵素はうまく働かない。65℃ジャストでなくてもいいから、50℃~70℃の温度をキープしておきたかった。
65℃、65ど、ろくじゅうごど、ごくじゅう、ご、ど……
念仏のように繰り返し唱えていると、ふと「火入れ」という言葉が浮かんだ。いつのことだったろうか、居酒屋で隣り合わせた男と日本酒について話した時のことを思い出す。
『最近俺さ、火入れ担当になったんだよね。兄ちゃん火入れってわかる?火入れって実は日本が誇る殺菌技術でさ。江戸の中期にはあったわけ。すごくない?』
小太りで、唐揚げを2個いっぺんに頬張っていたっけな……どうでもいい情報を思い出しそうになり、直は慌てて頭を振る。
『実は火入れの仕方にも何種類かあってさ。詳しくは企業秘密なんだけど、65℃で10分火入れってのが今のセオリーでさ。でも10分やるとちょっと熟成感が出ちゃうわけ』
「企業秘密」とか言いつつも、よくしゃべる男だったな……薄ぼんやりとした記憶を辿っていた直だったが、「65℃」というキーワードを思い出した瞬間に飛び上がった。
「そうだ!火入れ!火入れが65℃なんじゃん。やっべえ、俺天才すぎるんだけど!」
小さくガッツポーズをして、喜兵寿に向かって万歳をする。
「喜兵寿!火入れの温度だよ!日本酒の火入れの温度が、ビールの麦汁造りに必要な温度だ!」
喜兵寿は何事かと目を丸くしていたが、すぐに状況を理解し大きく頷いた。
「火入れ……なるほどな。では『手抜き』を保てばいいわけか」
手を入れ、5つ数える前に我慢できなくなる温度「手抜き」。それが65℃であり、酵素を働かせるために必要な温度なのだ。
―続く
※このお話は毎週水曜日21時に更新します!
協力:ORYZAE BREWING
※記事に掲載されている内容は取材当時の最新情報です。情報は取材先の都合で、予告なしに変更される場合がありますのでくれぐれも最新情報をご確認いただきますようお願い申し上げます。